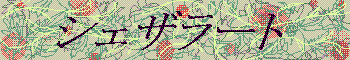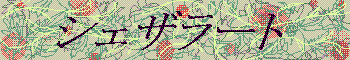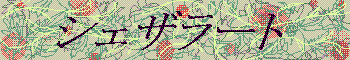
「お宅のお子さんは、このままでは長くもって一年でしょう。」
担当の医師から告げられてもう三日になる。
「い、一年なんて・・・。」
中学一年生になる娘は子供の頃からの難病だった。それが最近急速に症状が悪化し、入院生活が続いている。
「お母さん、あなたにいまさら言うまでもないが、あの病気の治療は、非常に苦痛を伴います。
それでいて、病気そのものを直す効果はない。これ以上の進行をなんとか押えることしかできません。」
医師の声は無情だった。確かに本当のことを隠さず話して下さいと頼み込んだのは自分だ。医師の立場では、希望的観測を言える
段階をとうに過ぎていたのだろう。それは真実であった。が、彼女が聞きたかったことではなかった。
「以前お話していた移植手術が、唯一の助かる可能性です。しかし、適合する臓器の提供者が現れ、手術可能になるのがいつになるか
わからない状態です。いつになるか・・・。」
まだ若い医師は、蒼白になっている母親の目をまっすぐ見つめた。
「あなたにこのことをお伝えするのは、おそらく一年以内のうちには移植手術が確実にできる見込みがついたためです。ただ、期日
は残念ながら直前まではっきりしないのです。」
「で、では・・・!」
「ぼくが一番心配しているのは、彼女の気力です。・・・実は、この病気の方を担当するのは和美さんが初めてではありません。その
患者さんは、毎日続く苦しい治療に生きる気力をなくし、急速に弱って、手術を待たずに亡くなられました。」
本当は絶望して這って窓までたどり着き、飛び降り自殺したのだが、さすがにこれは言えなかった。
「苦痛は人から気力を奪い、そして気力がなくなると、体力は恐ろしいまでにおとろえます。もし彼女に手術に耐えられる体力が残っ
ていなかったら、おしまいです。」
「・・・・。」
「だから、お母さん。あなたは娘さんをたえず励ましつづけてください。彼女に生きる気力を、生きていたいという思いを私達は与え
続けなければいけないのです。」
「気分はどう?」
病室に入っていった時、娘はぼんやりとベッドに横たわっていた。このところ、元気のない日が続いている。
繰り返し、毎回涙がこらえ切れないほど“痛い”治療を受け、なのに病気はいっこうによくなるきざしがないとわかってくれば、12才
の少女が意気消沈してくるのは避けられないことだった。
娘は母親をぼんやり見た・・・その目が片手の本屋の紙包みにすいつく。
とたんに、彼女の顔に生気がさした。
「今日・・・そうだ、発売日だったんだ!!」
娘が歓声を上げ、もどかしく袋を開け、隔週発売の少女マンガ雑誌のページをパラパラめくるのを見て、母親はほっとした。
小学生の頃から続いている大のお気に入りのマンガが、その雑誌には載っていた。
病院の売店には置いてないし、雑誌は入荷が毎回遅れるため、彼女がいつも本屋で買って持ってきていた。
病院では治療用機材が誤動作する恐れがあるため、電子端末の使用は制限されている。本やマンガが患者の無聊をなぐさめるための
必需品であることは、今もこれからも変わりなさそうだった。
初めのうちはこまめに訪れてきてくれていた友達も、近頃はやや足が遠のいている。陰で頼み込んではいるものの、新しい付き合いの方に
忙しくなっているのだろう。強制はできない。
夫は・・・おそらくこの病室に来ることはあるまい。昔から我が子の病気には冷淡な男だった。娘の入院後、愛人宅から帰宅した夫をなじり、
二度と顔を見たくないと自分が叫んだ言葉通りにしている。現在離婚調停中だった。娘は薄々察しているのか、「お父さんに
会いたい」とは一度も言わない。こればかりは、もう少し自分が堪えていれば―と、後悔する時がある。
娘は夢中になって読みふけっている。その連載マンガは―単行本になったものは娘が枕もとに持ち込んでいるし―
彼女も治療の待ち時間などについ読んでいた。
よくある恋愛マンガで、何が娘をそんなにも夢中にさせているかわからないが、確かに連載が長いだけのことはあり、人間というか
恋愛関係が複雑に入り乱れて、毎回トラブル、アクシデントが発生し、先が読みにくい、うまいというか小ずるい構成になっていることだけは
確かだった。
なにはともあれ、このマンガに彼女は感謝していた。つらい闘病生活を送る娘にとっての最大のイベントは、(他のことに目を向ける
のは制限がありすぎる現状だったし)このマンガ雑誌の発売日になっていた。夢中で読み終え、次の発売日をひたすら待つ。
母親が読んでいるのを知っているから、時々「最後にくっつくのはやっぱり☆☆は★★だと思う?」とかたあいもない会話を
親子でかわすこともある。
担当医師は、枕もとにずらりと並ぶマンガや単行本には何も言わなかった。
「ぼくも、子供の頃、週刊誌の連載マンガに夢中でした。あの頃はこづかいが少なかったから、毎週買うのはキツくて、発売日には
立ち読みのできる本屋に走ったものでしたよ。
なにはともあれ、和美さんに“待つ楽しみ”があるのは大変いいことです。」
彼は母親に廊下でそう言った。
「手術のほうは、いつ・・・。」
「まだ・・・ですね。それしか今はいえません。」
今日はマンガの発売日だ。いつものように本屋に行き、買う前についぱらぱらとめくる。娘の影響で、自分もかなり続きが気になる。
先に読んだら娘に悪いかなという罪悪感をちょっぴり感じつつ。
「・・・?」
見慣れたタッチのページがない。見落としたのかと、再びめくる。
見当たらない。あわててあちこちのページを繰った。
「・・・先生の“フラワーパニック”は、先生の急病により、休載になりました―」の文字が飛び込んできた。
「そんな・・・。」
娘のがっかりした顔がまっさきに浮かび、母親は蒼ざめた。
雑誌をいくら調べても、それ以上の記述はない。彼女もマンガ世代だから、自身の体験として、そういうことがあるのは知っている。
しかし、よりによって、娘が病院での闘病生活を余儀なくされている時に・・・。
時間もなく、重い気持ちで病院に行く。案の定、娘は泣きそうな顔になり、そのあとはいくらあれこれ話し掛けても表情はさえなかった。
病室に来た医師が一目で具合が悪いのかと問い掛けたほどに。
「仕方ないわよ。漫画家の先生だって、お腹をこわしたり風邪を引いたりすることはあるでしょう。
もう二週間待ちましょうよ。」
「うん・・・。」
しかし、半月後も、そのまた半月後も連載が再開されることはなかった。
「いったい、いつ連載が再開するんです!?」
雑誌社に電話をかけはじめたのは、二回目の休載の日の翌日だった。TVに出演したり、自らのHPでも持って積極的に自己アピー
ルをしない限り、通常、漫画家本人の素顔?は小説家以上に一般的ではない。(それに都会ならともかく、ここは地方都市だ。)娘
も、あれだけあのマンガがお気に入りではあるけど、作者については雑誌に掲載された程度しか知らない。
初めのうちは楽観していた。一時は落胆しても、また興味ありそうな対象の連載マンガを見つけさせればいいのだと、手当たり次第
雑誌を買い込んでは持って行った。同じ世代にもっとも人気のある、他の連載中のマンガの単行本を既刊分全部かかえて行ったこともある。
もちろん、他に―治療を受ける以外は―することのない生活だから、マンガを持って行けば、一応熱心に読みふけってはいるようだ。
しかし―
娘から何かが抜け落ちてしまったのだ。
そしてそれは、検査値にはっきり現れるまでになっていた。
医師の心配していた気力の減退・・・あんなどうでもいいようなマンガの続きに、それがかかっているなんて!
毎日通院している以上、消息を尋ねて都会に行くわけにもいかない。間接的なありとあらゆる手段をもちいて、情報をかき集めた。
雑誌の編集部も、娘が難病で、休載に気落ちしていると告げられては、邪険にあしらうわけにはいかないと思ったのだろう。
「実は・・・**先生は―もう、連載再開どころではないんです。」
「え!?」
「仕事中クモ膜下出血で倒れたんです。緊急手術を受け命は取りとめたものの、半身麻痺が残って、今まだ口も満足に動かない状
態です。リハビリを受け、なんとか体が動かせるようになるまでにはまだ長い時間がかかるでしょう。」
「・・・・!!」
「プライヴァシーにかかわることですので、このことは御内密に。娘さんにはお気の毒ですが・・・。」
クモ膜下出血という病気については知っていた。病院にいると、比較的元気な入院患者からあれこれ話を聞かされることがよくあ
る。出血の度合いによっては予後の悪い病気だということも。
電話が切れたあと、しばらく母親は目の前の壁を見つめていた。
病気。あの子の気力の生命線であるマンガの作り手が、同じく病に倒れ、再起不能になった。
どうすれば・・・。
あの子に絶対このことを告げるわけにはいかない。あの子が作者本人のファンなら、一緒に病気に負けないようがんばりましょう
ね、と陳腐なセリフでもささやける。
だがあの子が夢中なのは、作者ではなく作品そのものなのだ。それは痛感している。だから代替が効かない。
おそらく作者が復帰するには年単位の時間が必要なのだろう。それは応対した人間の口ぶりと自分が見聞きしたことから推し測られた。
小説家なら口がきけるようになれば口述もできる、病室からでも作品は発表できる。しかし緻密な作業と複数の人間を必要とするマンガは
そういうわけにはいくまい。
間に合わない・・・・。
母親はともすれば重い顔になる自分の顔を鏡でムリに矯正して病院に向かった。
しかしそこに待っていたのは、さらなる不幸だった。
「目が、目が見えないの・・・右目が全然、左目もなにか黒い物がゆらいで・・・!!」
娘は泣きじゃくってとりみだしていた。
眼球の硝子体への出血が両眼に急に起こったのだ。
レーザー凝固で網膜の出血は押えることに成功したものの、すでに硝子体に流れ出た血液については自然に吸収されるのを待つしかないと
いうことだった。眼球内にたまった血が入ってくる光をさえぎり、一時的な失明状態をつくりだしたのだと母親はあとで医師に聞かされた。
「普通は1〜2週間で引いてくるものなのですが、出血量が多かったのと病気の影響で、和美さんの場合何ヶ月か、かかると思います。」
「手術とか・・・なにかすぐ見えるようになる手段はないのですか!?」
「病気の進行にしたがって毛細血管がもろくなっている今の状態では、手術してもまた再出血する恐れがあります。この手術となる
とかなり大がかりなものになりますし、今は手術すべき状態ではありません。
むろん移植手術のほうが終わった後なら、目の方の手術はいつでもできます。」
「・・・・・。」
医師の口ぶりでは、一時的な失明などたいしたことのないような口ぶりだった。真っ暗な怒りが込み上げ、思わず殴ってやりたい思いにかられた。
「目が見えなくなって、もうフラワーパニックが連載再開されても二度と見ることできないまま死んじゃうんだ!!」
これまでどんなに苦しくても、死ぬという言葉をいっさい口に出さなかった娘だった。そして、絶望の最大の要因が、好きなマンガを
二度ともう見ることができないという恐怖からくるものだということを。
「一時的なものだそうよ。手足の内出血と同じで、中の血が吸収されたら徐々に見えるようになるんでっすって。」
「そんなのウソよ、病気だってちっともよくならないじゃない!!きっとこのまま私死んじゃう!!!」
ついに軽い安定剤が処方され、激しい興奮状態からようやく眠りが訪れた時、外はもうすっかり夜になっていた。
母親は廊下に出て、フロアのビニール張りの椅子に腰をおろした。見えないとわかっていても、くたびれ果てた顔を娘にむけるのは
いやだった。
本当のことを言ったら、娘は絶望して生きる最後の気力さえ失ってしまうかもしれない。連載休止でさえなければ、話のあらましは毎回
自分が話してやれるし、いずれはまとめて読もうという楽しみもできる。
あのマンガは長かった連載のクライマックスにさしかかっていて、いろいろなイベントやアクシデントが集結し始めた矢先だった。
作者本人にはムリでも、アシスタントや一緒に働いていた者なら、この先のおおよそのあらましを知っているのではないか?なんとか
それだけでも聞き出せば・・・。
ダメだ。連載マンガで毎回小出しにして話が“いいとこ”で切れてしまうから続きが気になるのだし、だから娘も次をひたすら待つ楽し
みができたのだ。かりに☆☆と★★が最後どうなるかの極秘情報?を入手できたとしても、それ一度かぎりのことだ。しかもそれをすると、
娘に連載再開のめどがまるで立たないことを打ち明けなくてはならなくなる。
神様、あの子のたったひとつの楽しみさえ取り上げるなんて、あんまりです。12才の子供が、大人の何人分もの苦痛を受け続けているというのに、
それに対する唯一の救いすら許さないのですか。
もし私が・・・・・。
母親の表情が変わった。ひざに置いた手をぎゅっと握りしめる。
「和美ちゃん、持ってきたわよ。」
娘はアイマスクをつけて寝ていた。起きているようだが、反応がにぶい。目が見えなくなってからというのも、それまでとはうってかわって気難しくなり、
治療の時も痛いとヒステリックに騒ぎ立てることもあって、かなり情緒不安定になっている。騒ぐ割に体力が低
下しつつあるため、すぐぐったりしてしまう。好きなマンガの単行本を読み返すことさえ出来なくなったのだから。左目はわずかにお
ぼろな視力は残っているものの、むりに見ようとするとよくないとのことで、アイマスクをかけさせられていた。
「なに・・・・。」
「マンガ。」
「・・・・・。」
「フラワーパニック、また連載始まったわよ。」
「ほんと!!」
ふだんならひったくるところだが、見えないのでそれが出来ない。ただ、突然鬱々とした(目は隠れてはいるが全身でわかる)
様子がふっとんだ。
「なんて書いてあるのか読んであげるからね。」
「う、うん!!・・・ああ、目が見えたら!」
「連載始ったんだから、見えるようになってからまとめて読めばいいわ。」
「そうだね―それより早く読んで!」
「ちょっと 待ってね・・・」
雑誌は確かに買って持ってきていた。しかしもちろん連載は再開されてはいない。彼女が見ているのは開いたノートのほうだった。
あの夜ひらめいた一つの啓示。それは、何日間か眼球内の様子を検査した眼科医が、すぐの手術は不可能なことと、視力回復には
何ヶ月もかかるだろうと診断 したことで決定された。
―作者が出来ないのなら、自分の手でもう一つの“フラワーパニック”を作り出すしかない―
娘につきあって単行本も初めから読んでいる。まだ単行本化されていない連載中の分も休載まで読んでいる。そして娘にはまだ話した事はないが、
高校生の頃、マンガではなく耽美系小説にはまって、サークルを作り同人誌めいたものを発行したことさえあるのだ。
あの頃だって、既成キャラを“さもありなん”風にヤオイ化して楽しんでいたではないか。同じことだ。
出来ないはずがない。いや、やらねばならないのだ。
娘のために。
決意してからマンガの発効日までには一週間あった。単行本をまた全巻買い、家にある雑誌を読みふけった。目が見えなくなてから、
マンガ雑誌の方は大半自宅にそっと持ち帰っていたが、休載になる前の号を、それこそ穴のあくまで読み返した。いかにももっともらしく、
かつそれっぽく、そして―ここが一番大事なとこだが―“いい局面で”「次号」に持ち込むよう話を押えておかなければならない。
なんとかそれらしい雑誌一回分のあらすじが完成したのは、雑誌発効日の前日だった。
母親が“読んで”いるのは自分で描いた超ラフな構図と、そのセリフ(むろん自分で考えた)、絵は描けないがそれを文章で説明しようとしたら
こうなるであろうかという、多量の書き込みのあるページだった。
初め大ざっぱにストーリーを話し、あとで娘の求めに応じて各場面の説明をしていった。
娘が途中で不審がるのではないかと気が気でなかったが、幸い、繰り返して“大事な”シーンの描写を聞き返す以外は、まったくそ
の様子はなかった。ただ、
「よかった〜。このままずっと休載で終わってしまうんじゃないかともう思っていたの。
・・・やっぱり、あきらめちゃいけないんだね。何でも。」
としみじみと言われた時には、良心がひどく痛んだ。それでもこう言わざるをえなかった。
「病気になってずっと入院していたんですって。もうよくなったとコメントに書いてあるけど、和美ちゃんもがんばりましょうね。よくなっ
たらマンガも自分の目で読めるようになるんだし。」
「うん。本当にそうだね。」
屈託のない笑顔が向けられ、安堵と疼きが一緒に胸をさした。
「ああ・・・、この次は▲をどうしよう。どうしても死んでもらわないと先が困るのだけど、和美は▲がけっこうお気に入りキャラのようだし・・・
そうね、しばらくハラハラさせる場面を作って―」
自宅の台所のテーブルにノートを置いて、母親はため息をついた。急須の中で冷えてしまったお茶を湯飲みに注ぎ、味も感じぬまま
飲み干す。
娘の苦悩を見かねて思わず始めたことであったが、素人がいきなり、何年にもわたって積み重ねられたストーリーの続きをでっち上
げようとするのだから、生半可な苦労ではなかった。
簡単だったのは、連載休止直前の流れに沿っていられたうちで、いつまでもそこだけ“描写”しているわけにはいかず、大勢の登場人物の
一人一人の展開は、もうまったく自分の作り上げた新しい筋書きで動いてもらうしかない。
話を単調にしてしまえば語るにはラクだが、それでは娘の次回への渇望をよべなくなり、それは生きのびて続きを読みたいと思う気持ちを
萎えさせてしまう。
苦しい闘病生活の中、次々と閉ざされていく希望の扉。人間はどんなに辛い時でも何かのささえがあれば、それをたよりに進んでいける。
それがあの子にとってたまたま、あのマンガだったのだ。
それを絶やしてはいけない。
千一夜物語のヒロイン、シェザラート。あなたは語れなくなったら、残忍で気まぐれで好奇心だけは強い夫に自分が殺されてしまうから、
千一夜もの間語りつづけた。
そして私は語れなくなったら・・・娘を殺されてしまうのよ。・・・病魔に。
語りつづけなくてはならないの。あの子の病魔がその手をかけないように。
二週間ごとに娘に雑誌を持って行き、その場で語って聞かせる。娘の病室に出入りする看護婦には、婦長を通じて事情を告げていた。
病院にいる時間が長くなると、看護婦が決して白衣の天使だけではないことはわかってくる。自分が話している時に、よこで不用意な一言でも言われたら
水の泡だ。
連載何回分かが過ぎ、話は次第に母親作の完全オリジナルな展開にはいっていった。つじつまをあわせるため、今まで登場していなかった
新しいキャラまで作り出した。
目の見えない生活に次第に慣れてきている娘になにか感づかれはしないかと薄氷を踏む想いではあったが、いったんつきはじめたウソは
途中では止められない。
娘の目がもし予想よりずっと早くよくなって見えるようになったら・・・一番喜ぶべきことなのに、それを恐れなくてはならないなんて。
今のところ、新しい眼底出血だけ抑えるのが精一杯で、硝子体にたまった血液は、移植手術が終わった後、あらためて手術して取り除く方針に
変わりはないらしい。
移植手術が終わり、目の方もよくなれば―そう、私は娘をだまし続けた罰を喜んで受けよう。たとえ娘が一生そのことを
許してくれなくてもいい。
あの子が元気になりさえしたら!病気がよくなり、学校に行くようになれば、新しい生活の中であのマンガは忘れられていくだろう
が・・・。
自宅で単行本を机いっぱいに広げ、草稿を作る。病室でメモを取る時もあるが、だんだん音のカンがよくなっている娘に不審がられてはならない。
一度、
「お母さん、ほんと話すのがうまいね。まるで目に見えるようだよ。」
と言われた時はどきっとした。
本来マンガは視覚的に作られているので、意外とページに何が描かれているか言葉で表現するのは難しい。
(マンガにもよるが。背景に薔薇の花を背負ったシーンなど、直接表現ではどう言えばいいのだ?)
だが、自分の草稿は一応簡単な構図は描いてはあるものの、すでにビジュアルノベルになっている。本物の“フラワーパニック”の
シーンより、その点では朗読向きであった。
二週間ごとに、とにかく娘をハラハラ、ドキドキ、ワクワクさせる展開のある話を作り上げることは、毎回大変な作業だった。看病と創作と気苦労の日々が続いてる。
しかし、娘は毎回本気で夢中になって母親の創作した話に聞き入り、次の発売日を待ち望むのだった。
連載でいったらあと数ヶ月分のおよそのストーリーはすでに出来上がっていたが、口述向きに再編するのは、それ以上に手間取った。
だが、今日ははかどった。
先日、移植手術の見通しがたったと、ついに告げられたのだ。
手術の成功率は決して楽観できるものではないとも聞かされたが、母親はプラスのイメージばかりを思い描き、マンガのストーリー
製作に没頭することで、確率の陰の部分に頭を使うことを拒否していた。
一段落ついて、病院に向かうと、娘の枕もとに小ぶりのかわいいぬいぐるみが飾ってあった。ピンクのリボンで飾られている。
「どうしたの、これ。」
「宏子ちゃん達が、お見舞いに来てくれたの。」
「まあ、ごめんなさいね。今日ここに来るのが少し遅れてしまって・・・。」
「ううん。みんな、いろいろ学校のこと話してくれたよ。元気になったら遊ぼうって。」
娘は少し疲れているようだった。このところ友達もめったに来なくなっていた。久しぶりに会ったとはいえ、目が見えないので
かえって憂鬱になったのかもしれない。自分がいたら、もっと引き止めておけたのに・・・。
「お母さん・・・」
「なあに。」
「・・・なんでもない。早く手術を受けたいな。学校に行きたい。」
「もうじきよ。」
娘の手を取る。握り返すその手の細さと弱々しさに、急に不安な思いがよぎった。
手術の日が来た。
「何も心配することないのよ。お母さん、外で待ってるからね。がんばるのよ、和美ちゃん。」
「うん。」
一見、娘は母親よりも落ち着いているようにみえた。手術に対する恐怖より、毎日の苦痛に耐える日々とさよならできるという期待感のほうが
まさっているのだ。
あれこれ書かされた手術の同意書などの文面に、娘が手術に失敗して亡くなる可能性の確率の高さを、あらためて思い知いしらされた。
マンガ話を作る創作行為に逃げ込んでいた自分の甘さを痛感したのは手術間際だった。
治療が進行を抑えるといっても完全ではない。 多臓器不全におちいったら、そこでもう終わりなのだ。
手術直前の物々しく重い雰囲気の中で、娘はとても小さくみえた。
「お母さん・・・」
「なに?」
「フラワーパニックのことなんだけど・・・」
「雑誌の発売日はあさってよ。大丈夫、買っといてあげるから。手術が終わってから話してあげる。」
その時、手術着を着た大勢の人々がはいってきて、娘をドアの向こうに連れ去った。
待っている間の緊張と不安を、今ではどこに行くにも持参している創作ノートに書きこむことでまぎらわす。娘の生死にかかわる時に
こんなことしてるなんて、と唇をかむけど、ほかにしてあげられることもない。祈るだけなら、もう神様も食傷するくらいしている。
「手術は成功です。」
ようやく待ち望んだ言葉が聞けたのは、精神的疲労で目の前の床が波打って見えるようになりはじめた頃だった。ノートが床に落ちる。
「本当ですか!!」
「大手術でしたが、お子さんはよくがんばりました。」
喜色満面の母親に、専門用語で話す事しか慣れていないらしい医師は、その後たんたんとわかりにくい経過報告を
説明してから去った。
ここ何日間ほとんど寝ていない母親は、安堵したとたん睡魔におそわれ、くずれるように廊下の椅子の上で眠り込んだ。看護婦が
毛布を持ってきてかけたのにも気がつかなかった。
その頃、どこかの扉の向こうでは、決して楽観視されない報告が密かになされていた。
それは手術後まだ半月もたたぬうちに現実となった。
「再手術!!?」
「手術は成功したって、言ったじゃないの!!」
担当医は、口になにか苦いものを詰め込まれているように話し始めた。
「・・・。そうです。移植手術そのものは大成功でした。しかし・・・以前、動脈瘤ができていることはお話ししましたね。病気の影響
で。」
「・・・。」
「しかし、その動脈瘤が、外部からのあらゆる検査結果を上まわる危険なものであることが手術中にわかったのです。とりあえず応急処置をして
手術は続行されました。経過を見ていたのですが―ここ数日、その結果が思わしくないんです。
ここの動脈瘤が破裂すると即、大出血をひき起こし死にいたります。起るのを待ってから手術したのでは、成功率は限りなく低くなる。」
「そんなこと、何も今までおっしゃらなかったじゃないですか!!」
「・・・。」
「また手術なんて!これで元気になれるってあんなに喜んでいるのに。」
母親の呪詛に近いののしりを、医師は黙って聞いていた。移植の大手術のあとにすぐまた再手術をうけることがどういうことか、彼には母親より、
よくわかっていたのだから。手術の成功率は、動脈瘤が破裂してから手術するよりは高いが、移植手術のそれより低い。
だが放っておけば、古い風船に血を一杯につめて振り回しているようなもので、ベッドの上でわずかに身動きするような動きでも
命取りになる。あの娘はおそろしく辛抱強くがんばりやで、今回の移植手術の成功はあの娘自身のおかげともいえたが、
こればかりはどうしようもない。引き伸ばしてきたが、もう限界なのだ。母親がなんと叫ぼうと、再手術は必要だった。
それがどんな結果をもたらすことになろうとも。
「ほんと、また手術なんて、やだなあ。」
娘の声は明るかった。医師にはかって、再手術といっても、簡単なものであり、たいしたことないということにしたのだ。
だから本人は、ちょっとした術後経過の検診気分でいるようだ。それだけが救いだった。
緊急を要するため、あれからあわただしく準備がなされ、(といっても再手術は移植手術のあとすぐ検討されていたのだろうが)また
同じ光景が―二度も見ることになってしまった―始まろうとしている。
あまり、緊張した様子を声に出してはいけない。娘はこれを単なる検診程度に思っているのだ。だから、がんばってねとはげますこともできない。
涙がでてくる。見えないのが幸いだった。しかし涙声になってはいけない・・・。
「お母さん。まだ手術まで時間はあるよね」
「?」
「あのね・・・フラワーパニックの続き、話してほしいの。」
手術後、娘が意識が戻ってまっさきに聞いたことといえば、マンガの続きだった。あきれるより先に思わず抱きしめてしまったことを
覚えている。
「発売日はまだ先よ。手術が終わってからになるわ。」
「お母さん・・・。私、知ってるの。あのマンガ、まだ連載再開されていないこと。」
「・・・!!」
「手術の前、宏子ちゃん達が、お見舞いに来てくれたとこがあったでしょう。あの時、晶ちゃんも一緒に来てたの。」
晶・・・ああ、晶ちゃんね。小学校の頃は仲よしだったが、娘が入院後は一度も見舞いに来なかった。
「あの時、晶ちゃんが枕もとに置いてた単行本見て、言ったんだ。連載中止になって、残念だったね。でも、きっとまた目がちゃんと
見えるようになった頃、連載再開になるだろうって。」
「!」
お見舞いに来てくれる子供達には、「和美は連載休止になってがっかりしているので、あの子の前ではあのマンガの話はしないで
ね。」とさりげなく口止めしていた。しかし、娘があのマンガが大好きなことを知っている人間が、自分の不在の時に突発的に
来ていたとは・・・。
「ほんと、びっくりした。お母さんはずっと続きを話してくれているのに。
しばらくわけがわからなかったけど、お母さんが自分で続きを作って話してくれていたんだってことに気づいたの。」
「和美・・・。」
「ショックだった。でも、お母さんの話はとても面白くて、私全然気がつかなかった。それに、お母さんは私のために、
一所懸命話を作ってくれてたんだよね。
ほんとのことがわかってからでも、私、お母さんの話を聞くのが楽しみだった。毎回どうなるかわからないんだもの。いつも、『その先
どうなるの??』って口に出しそうで我慢するのが大変だったよ。」
「・・・・。」
今だ目が見えぬ娘の笑顔がそこにあった。
「お母さん・・・お母さんの話が聞きたいの。
お母さんの結末が聞きたいの。
わかってる・・・目が見えなくなってから雰囲気がかえってよくわかるようになったの。今度の手術が簡単ですぐ済むもんじゃないってことも。
ひょっとしたら、二度と目覚めないかもしれない・・・それは怖くない、でも最後がどうなるかだけは知りたいの。
お願い、お母さん、話して!」
本当にそうかもしれなかった。娘が生きて手術室を出られる可能性は低いのだ。
それならば、願いどおり、自分で考えた結末を今のうちに話してやるのが最後の―愛情ではないのか。
しかし、彼女の心の中のもう一つの声がそれを強固に押しとどめていた。
今話せば娘は満足するだろうが、結末を知ったことであれだけあった生への執着心が薄れ、そのため手術が失敗したら・・・?私の
創作と知ったあとでさえ、あの子はあんなに続きを本気で聞きたがったではないか!
医師も驚く気力は、まさにあれからもたらされたものなのだから。
ここは、心を鬼にしてでも結末を教えないほうが、娘の命を救うことになるのではないだろうか。
しかし、もし・・・だったら、私は娘の最後の願いさえ聞いてやらなかったことになる。
私は・・・。
永遠と思われた逡巡のあと、期待に輝やいているやせこけた娘の顔にむかって、母親は微笑み、口を開いた。
―了―
―夢見の井戸に戻る―